B型(円筒型)とE型(コーンプレート型)の粘度計の特徴とは
粘度計にはB型とE型の2種類があり、これらは試料に応力を加える方法に大きな違いがあります。B型の粘度計は容器に入れた液体に回転する回転子(スピンドル)を挿入して定速で回転させ、スピンドルが液体から受ける抵抗(応力)を直接測定します。
E型の装置は2枚の円盤の間にゼリー状の試料を挟んで、片方の円盤を回転させて正弦波を入力した時に円盤が受ける応力を測定する仕組みです。B型は構造や原理が単純なので簡易的な測定に向いていますが、弾性率を得ることはできません。
E型は正弦波を使用するので高校レベルの物理(波動)の基礎知識が必要になりますが、高精度で粘度と弾性率の両方の数値を得ることができます。
両方とも粘度の数値を得ることができますが、測定を行う目的に応じてどちらかを選ぶ必要があります。流体の粘度を測定するために粘度計を選ぶ場合は、いずれかの装置の使い分けるための基準を知っておくことが大切です。
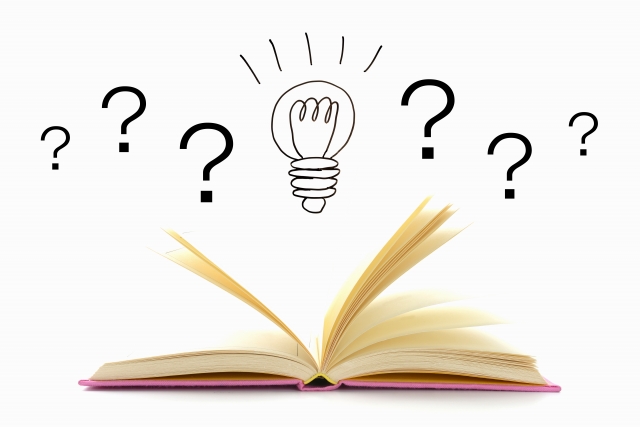
使用する粘度計の種類を選択する基準
水やオイルなどのように流れてしまう流体の粘度を測定する場合は、B型粘度計を使用すべきです。せん断応力に関係なく常に一定の粘度を持つ低分子の液体の粘度を測定する場合も、B型粘度計を使用することができます。
ポリマー材料のように、入力するせん断応力の値によって粘度の数値が変化するような場合はE型粘度計を使用する必要があります。粘弾性を持つ流体で弾性値を得たい場合も、E型を選ぶべきです。ある程度粘性の高い試料でもB型の装置で測定を行うことは可能ですが、粘性が高すぎると正しく応力を測定することができません。アスファルトなどのように粘性が高いゼリー状の試料を測定する場合は、E型を選択すべきです。
粘度の大きな流体に強い力で撹拌をし続けると、撹拌子の運動エネルギーが熱に変化して試料の温度が上昇してしまいます。試料の温度が上昇すると粘度が大きく減少するような場合も、E型を選ぶようにしましょう。

まとめ
粘度計にはB型とE型の2種類がありますが、試料の分子量や性状(液状またはゼリー状)を基準にして使用する装置を選ぶ必要があります。見た目がサラサラ流れる液体であればB型を、簡単に流れないようなゼリー状の試料やポリマーの場合はE型の装置を選ぶようにしましょう。
ちなみに粘度の値が非常に低くて流れやすいような液体を測定する場合には回転粘度計は不向きで、古典的な細管式または落球式の装置を使用する必要があります。

